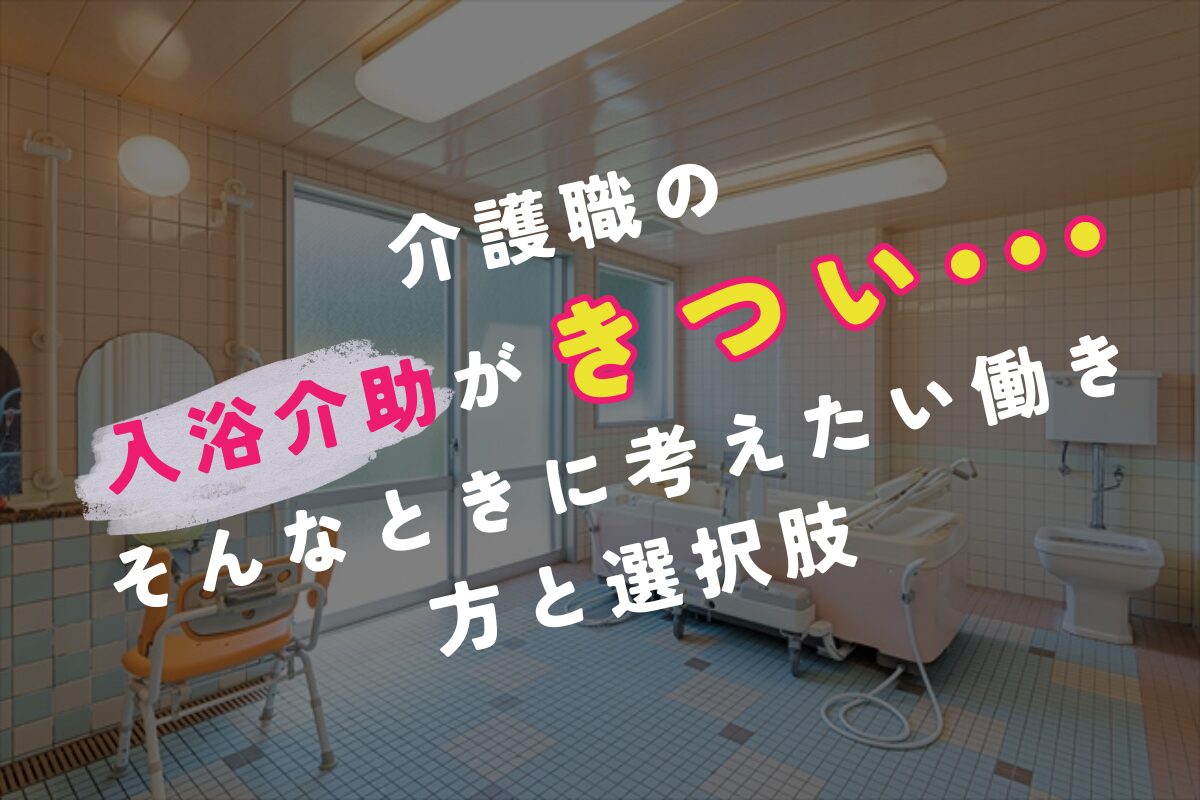介護職の中でも「入浴介助」は身体的にも精神的にもきついと感じる方が多い業務です。とくに新人のうちは慣れない動作や緊張感から、心身ともに疲弊してしまうことも。

私も入浴介助の日はいつもクタクタでしたね…
この記事では、入浴介助のきつさの理由や対処法、働き方の工夫についてお伝えしますのでぜひ参考にしてください!
入浴介助がきついと感じる主な理由
入浴介助が他の業務よりも「きつい」と言われる背景には、いくつかの理由があります。それは単に体力的な負担だけではなく、精神面や職場環境など複合的な要因が絡み合っていることが多いです。
詳しくみていきましょう。
体を酷使する動作の多さ
入浴介助は利用者の身体を支えながらの動作が多く、腰や腕への負担がかかります。とくに、立ち上がりの介助や浴槽のまたぎの動作は、体勢を崩しやすく、腰痛や筋肉疲労の原因にもなります。
こうした動作を繰り返すことで、慢性的な痛みや不調を感じる職員も少なくありません。さらに、高齢の利用者の場合はバランスを崩しやすいため、急な動きに対応するための反射的な力が必要となり、それがより大きな負担につながります。
緊張を強いられる精神的ストレス
浴室は床が濡れていることが多く、滑りやすい環境に常に気を配る必要があります。自分だけでなく、利用者の安全も守らなければならないため、動作のたびに集中力と注意力が求められます。また、入浴時は利用者が裸になるため、身体を支えたり動作を補助したりする際に滑りやすく、適切な支え方が難しくなる場面もあります。こうした状況は、転倒やけがなどのリスクを高める要因にもなり、職員にとって大きな精神的負担となることがあります。
さらに、転倒や溺水などの事故のリスクも高いため、絶対に事故を起こしてはいけないというプレッシャーが常にのしかかってきます。これらの要因が重なることで、入浴介助は身体だけでなく精神的にも強い緊張を強いられる作業となっているのです。
熱気と湿度による体力の消耗
浴室は温度と湿度が高くなりやすく、汗だくになって体力を消耗しやすい環境です。特に複数の利用者を連続して介助する場面では、休む間もなく作業が続き、疲労が一層蓄積されやすくなります。
夏場は特に過酷で、脱水や熱中症のリスクも高まります。こまめな水分補給が推奨されますが、忙しい時間帯にはその余裕すら持てないこともあり、体調不良を招く可能性も否定できません。
加えて、マスクを着用しての介助が求められる場合、蒸気と湿気でマスク内が蒸れて息苦しさが増し、呼吸が浅くなることで集中力や判断力が鈍る可能性もあります。
限られた時間内でのプレッシャー
多くの施設では、入浴介助にあてられる時間が限られているため、1人あたりの介助にかけられる時間が短くなります。特に人手不足が深刻な現場では、限られた職員で多くの利用者を効率よく入浴させる必要があるため、作業は常に時間との戦いです。
その結果、職員にはスピードと正確さの両立が求められ、常に緊張感の中で業務をこなす必要があります。時間内に終わらせなければならないという焦りは、身体の動きにも影響を与えやすく、思わぬミスや事故の原因となることもあります。
利用者との関わりによる心の負担
入浴というプライベートな場面では、利用者が不安や抵抗を感じることがあります。裸になるという行為に対して恥ずかしさを感じる方や、体調により入浴が億劫になっている方も少なくありません。そういった繊細な感情に寄り添いながら声かけをしたり、安心感を与える工夫をすることが求められます。
また、認知症のある方の場合には、入浴の意味が分からず拒否的な態度を示すこともあり、職員はその都度対応を変えながら丁寧に接する必要があります。その気持ちに配慮しながら対応することは、想像以上にエネルギーを使う作業であり、精神的なストレスにもつながります。
入浴介助のきつさを軽減するための工夫
入浴介助の負担を少しでも軽くするためには、日々の工夫が大切です。身体的な疲労を溜め込まないようにすることや、精神的に安心して業務をこなせる工夫を取り入れることで、継続して働くための土台を築くことができます。
以下では、現場で実践できる具体的な対策を紹介します。
正しいボディメカニクスを意識する
身体を痛めないためには、持ち上げる・支える動作の際に、腰ではなく脚の力を使うなど、正しい姿勢を意識することが大切です。
例えば、前屈みにならず膝を曲げて重心を落とす、利用者と自分の距離を近づけて重さを分散させるといった動きが有効です。無理な動作を避け、腰や肩に過剰な負担をかけないようにしましょう。
施設での研修やOJTを活用し、先輩職員から実践的なコツを学ぶことも非常に有効です。自分の動作を録画してチェックするなど、フィードバックを得る工夫も取り入れると、より安全な介助技術が身につきます。
2人介助をうまく活用する
介助が必要な利用者に対しては、1人で無理せず2人介助を行うようにしましょう。相手と息を合わせ、声を掛け合いながら介助することで、負担を分散させるとともに、事故のリスクも軽減できます。チームで協力し合える体制を作ることが、安全な入浴介助の基本です。
また、2人介助が必要かどうかの判断基準を職員間で共有しておくと、対応がスムーズになります。あらかじめ役割分担を決めておくことで、スムーズな介助が可能になります。
汗対策や水分補給も忘れずに
吸汗速乾のインナーやタオルを用意し、こまめに水分を摂ることで体調管理に気をつけましょう。特に夏場は脱水症状を防ぐためにも、入浴前後に飲み物を準備しておくことが推奨されます。
入浴介助後は、できるだけ短時間でも座って休憩を取るよう心がけましょう。冷房の効いた休憩室や、扇風機などで体温調節ができる場所の確保も重要です。自分の体調と向き合い、適度に休憩を入れることで、パフォーマンスを保ち続けることができます。
つらいと感じたら早めの相談と環境の見直しを
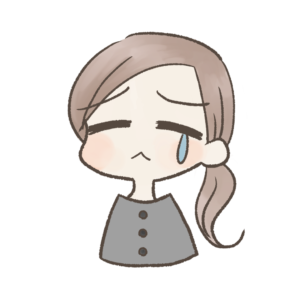
無理をしすぎると、体だけでなく心も壊れてしまいます。
つらさを我慢せず、早めに行動をとることが大切です。
先輩や上司に相談する
現場での悩みは、1人で抱え込まずに相談することが大切です。日々の業務で困っていることや不安に思っていることは、声に出すことで状況が変わるきっかけになります。
入浴の手順の見直しや、利用者との相性を考慮した担当の調整、作業工程の改善など、相談することで現場が柔軟に対応してくれるケースも多くあります。
相談することで、ひとりで頑張らなくていいんだと感じられ、気持ちが軽くなることもあります。職場内で信頼できる人との関係性を築いておくことも、ストレス軽減に役立ちます。
働く環境の見直しも一つの手
どうしても入浴介助がつらいという方は、無理をせずに働き方を見直すことも大切です。たとえば、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの身体介助が多い施設ではなく、訪問介護やデイサービス、サービス付き高齢者向け住宅など、入浴の頻度が比較的少ない職場を検討するのも選択肢の一つです。
また、事務作業中心の職種や、利用者との関わりが限定的な業務に移ることで、身体的・精神的な負担を軽減できる場合もあります。自分に合った働き方を模索することは、長く介護職を続けるためにも欠かせない視点です。
働き方そのものを変える選択も視野に入れて
入浴介助などの身体介助に強い負担を感じている場合でも、「介護の仕事自体は好き」「人と関わることは続けたい」と考えている方は少なくありません。

そのような方は、働き方の方向性を変えることで、無理なく介護職を続けることができる可能性があります!
入浴介助の少ない職場を選ぶ
すべての介護施設で入浴介助が同じように行われているわけではありません。職場によっては、そもそも入浴介助の回数や人数が少なかったり、専門の入浴スタッフが配置されていたりするケースもあります。
たとえば、サービス付き高齢者向け住宅では利用者が自立していることが多く、入浴介助の負担は比較的軽めです。
また、デイサービスや訪問介護なども1日に対応する人数が限られており、施設系に比べてゆとりあるスケジュールが組まれていることが多いです。これらの職場であれば、心身の負担を抑えつつ介護の仕事を続けることができます。
入浴設備や研修が整った職場もチェック
職場によっては、機械浴やリフト浴、入浴用ロボットなどの設備が整っており、職員の身体的負担を大きく軽減してくれる場合もあります。利用者を持ち上げる動作が不要になることで、腰や腕への負担が少なくなり、けがのリスクも低減されます。
また、定期的に入浴介助に関する研修が行われている施設では、安全な介助方法を学びながら働くことができるため、未経験者やブランクのある方でも安心して業務にあたることができます。こうした職場を選ぶことも、入浴介助のきつさを減らす大きなポイントです。
経験を活かして広がるキャリアの選択肢
これまでの介護経験を活かして、相談員やケアマネジャーといった上位資格を目指すことで、現場の第一線から少し離れた形でのキャリアアップが可能です。利用者や家族との調整、サービス計画の作成などが主な業務となるため、身体介助の比率が減り、経験を活かしながら長く働くことができます。
さらに、医療事務や福祉関係の事務職への転身を考えるのも一つの道です。デスクワークが中心の職種であれば、身体的な負担はぐっと軽減されますし、事務処理スキルやパソコン操作などを身につけることで、将来的に職域を広げることもできます。
このように視野を広げてキャリアアップやキャリアチェンジを目指すことで、自分の得意や希望に合った働き方に近づくことができます。
自分のペースで働ける環境を見つけよう
入浴介助がきついと感じることは決して珍しくありません。誰しも最初は戸惑いながら覚えていくものです。
しかし、どうしても体や心がつらいときは、無理をせず、自分に合った働き方を見直すことも大切です。介護職は幅広い働き方ができる仕事です。自分に合った場所で、自分らしく働いていきましょう。